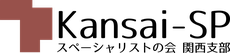平成26年度合格者体験記
ここでは現在、空間情報総括監理技術者の合格を目指しておられる皆さんに、空間情報総括監理技術者試験対策に関する情報を提供いたします。

「空間情報総括監理技術者への道」合格者体験記
1.自己紹介
氏 名 : 芝 隆(しば たかし)
勤務会社 : 国際航業株式会社
専門分野 : GIS構築、プロジェクトマネジメント
受験の動機 :
業務を実施する上で必要だったことが、受験の動機としては一番大きいです。弊社では、空間情報に携わる技術者は、技術士の合格など受験資格が取得できれば空間情報総括監理技術者にチャレンジすることが組織文化として定着しているように思います。もちろん、技術者としての自己研鑽のためでもありました。
2.受験に当たり事前に準備したこと
受験に当たり事前に準備したことは、以下のとおりです。
①日本測量協会のホームページに掲載されている過去問題から、問題の傾向を分析しました。
②日本測量協会発行の学会誌「測量」のテクニカル・レポート及び連載企画から、過去1年間で話題となっている技術を調べました。
③日本写真測量学会の学術講演会や応用測量技術研究発表会、地理情報システム学会の学術大会で近年、発表されている論文を調べました。
④国土交通省、国土地理院、総務省、日本測量協会などのホームページから、空間情報技術の動向、トピックスを調べました。
⑤弊社内で開催される空間情報の勉強会に参加し、情報収集に努めました。
⑥調査した技術情報が自身の業務ならどのように活用できるか、仮説を立ててみました。
3.合格してから変化したこと
個人の意識の変化として、空間情報の技術動向並びに業界の活動に対して、今まで以上に関心を持つようになりました。また、管理技術者、担当技術者を担当する場合、技術力を証明する上で資格を有していることが求められることが多いですが、空間情報総括監理技術者は業界内での認知度が上がっていることから、弊社内での重要な業務に、これまで以上に携わる機会が増え技術キャリアがアップしたように思います。
当然、「スペーシャリストの会」に入会できたことは人脈形成において大変有意義でした。
4.これから受験する人へのアドバイス
周りの空間情報総括監理技術者から受験対策として実施したことを、聞かせていただくことが一番良いと思います。聞かせてもらった話の中には、自分に合う対策が必ず見つかると思います。
また、文章の書き方、伝え方は、試験前に習得しようとしても急には身につかないと思います。課題の絞込み、問題を分析する論理的思考を日常の実業務の中で意識し、気にかけておくと試験では大いに役立つと思います。
以上
「空間情報総括監理技術者への道」合格者体験記
1.自己紹介
氏 名 : 川上 崇
勤務会社 : 株式会社日建技術コンサルタント
主な専門とする業務分野 :
写真測量、GIS、下水道の固定資産調査及び評価業務など
受験の動機
私は、平成26年度に空間情報総括監理技術者試験に合格しました。近年、地方自治体の発注業務では、この資格が条件とされている業務が増えてきており、受注確保のため、会社として資格取得に向けて取り組んだのが、受験のきっかけです。
ただし、私個人としても、いつか取得したいと思っていました。測量士は、指定の学科を卒業すれば、実務経験だけで取得できることから、建設業界内では、地位が低く見られがちです。また、技術士の選択科目に「測量」や「GIS」、「空間情報技術」が無いため、技術者としてのモチベーションを保つことができず、卑屈な気持でいました。そんな時に、この資格の存在を知り、測量分野の最高峰の資格ということで、憧れを持っていました。
当時は、まだ技術士を取得していなかったので、技術士を取得してから受験しようと思っていましたが、情報処理技術者(応用情報)と地理空間情報専門技術者(GIS1級)等の資格で、受験資格が得られるということが分かり、受験することになりました。
また、当時、日本測量協会の会長であった村井俊治先生が、日本測量協会主催の講習会で言われた言葉が、私の意識に変化を与え、この資格を取得したいという気持ちをさらに強くしました。正確な言葉は忘れましたが、「学歴や地位に囚われず、創意工夫やイノベーションのアイデアさえあれば、誰でも努力すれば実現することができる」というような内容であったと思います。高度な仕事は大企業でないと出来ないと思い込んでいましたが、それは自分の考え方次第なのだということに気付き、一念発起し、受験勉強に取り組みました。
2.受験に当たり事前に準備したこと
①技術士の受験勉強
私は、この試験を受験する前から、技術士(情報工学部門)を目指して、10年近く前から情報工学の勉強をしていました。土木工学科卒なので、情報工学の基礎から、かなり勉強したと思います。仕事が忙しく、受験勉強は少しずつでしたが、毎年、IPAの情報処理技術者の試験を受けるなど、コツコツと自己研鑚はしていました。
技術士は、「技術は何か、課題は何か、工夫したことは何か」という部分が明確に説明できないと合格できません。この技術士の勉強自体が、空間情報総括監理技術者試験の合格に必要であったと考えています。
私は、平成26年度に空間情報総括監理技術者試験に、1回目の受験で合格することができましたが、それまで長い間、技術士を目指して勉強していたことが役に立ったのだと思います。ちなみに、翌年の平成27年度に技術士(情報工学部門)に合格する事ができました。
②月刊「測量」の精読
受験にあたっては、過去2~3年分の月刊「測量」を精読しました。それまでは、流し読み程度の感覚で読んでいましたが、受験中は、一つ一つの記事を理解するよう意識して読みました。そうすると、今まで気が付きませんでしたが、面白い記事や論文もあり、楽しんで勉強することができました。
③過去問を解く
日本測量協会のHPで過去問が公開されています。この過去問を実際に自分で解いてみました。実際に解いてみると、時間がまったく足りないことがわかります。一つの問題だけでも調べ始めると簡単に1日が過ぎてしまいます。ただし、この時作成した答案は、試験当日に大変役に立ちました。この試験では、参考資料を持ち込むことができます。試験では、過去問と同じ問題は出ないと思いますが、作成したデータは素材として活用することができるので、時間の短縮に繋がりました。
3.合格してから変化したこと
合格して変化したことは、まず、会社内での職位が上がり、それにより昇給もしました。ただし、一番変化したと感じるのは、以前より忙しくなってしまったということです(喜ぶべきことなのかもしれませんが、複雑です・・・)。
また、スペーシャリストの会に参加することにより、勉強会への参加や、講師としての活動などもあり、技術者としての幅が広がります。
4.これから受験する人へのアドバイス
試験には参考資料を持ち込むことができるので、暗記して解答できるような問題は出題されません。試験に合格するには、文章の読解力や表現力など基礎的な要素は必要ですが、最も必要なことは、今までどれだけ空間情報技術に携わってきたか、また、これからの空間情報技術はどうなっていくかなど、日常的に空間情報技術に思いを馳せ、取り組んでいるということを証明することだと思います。私自身、受験を通して、今までの仕事を見つめ直す良いきっかけとなりました。
この資格は、測量業界を活性化、発展させるための資格であると思っています。測量業界に長く携わっている方や、空間情報技術が好きな人にはぜひとも取得してほしいと思います。
以上
空間情報総括監理技術者 Spacialist
スペーシャリストとは、Spatial(空間)とSpecialist(専門家)を合わせた造語です。
スペーシャリストの会の使命は、地理空間情報の専門家集団が自主的な活動を通して、我が国の地理空間情報の発展の先導的役割を果すことです。